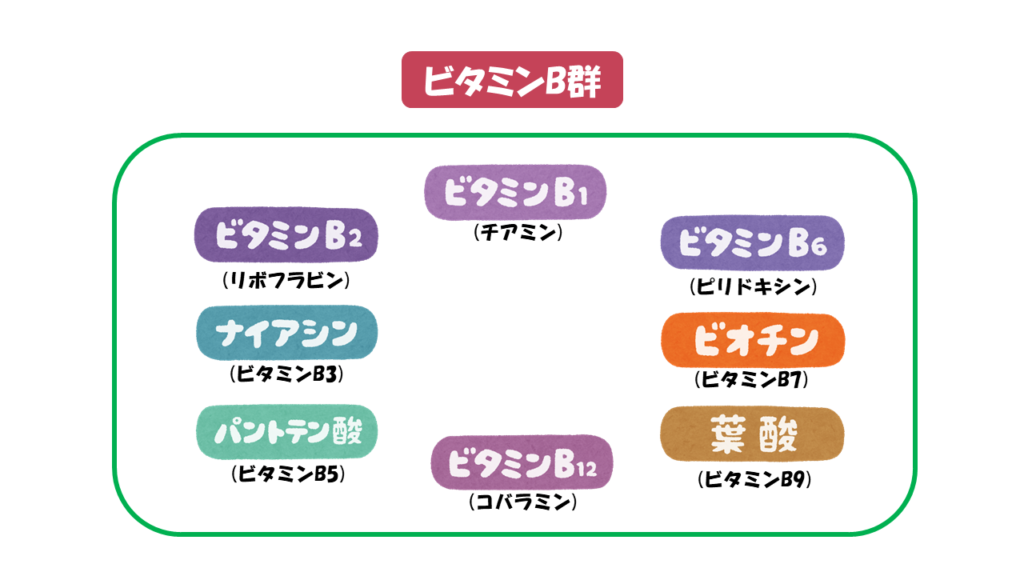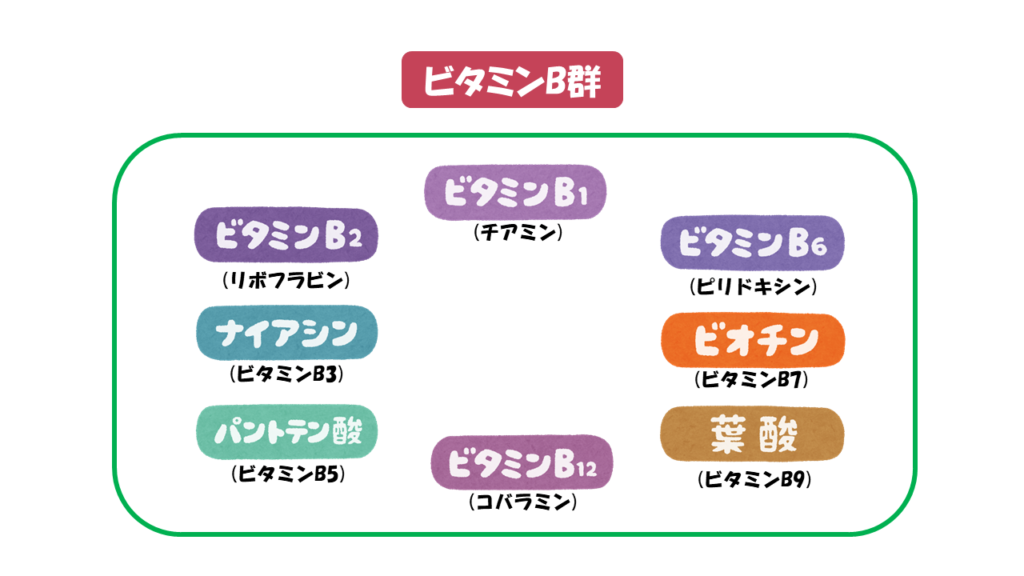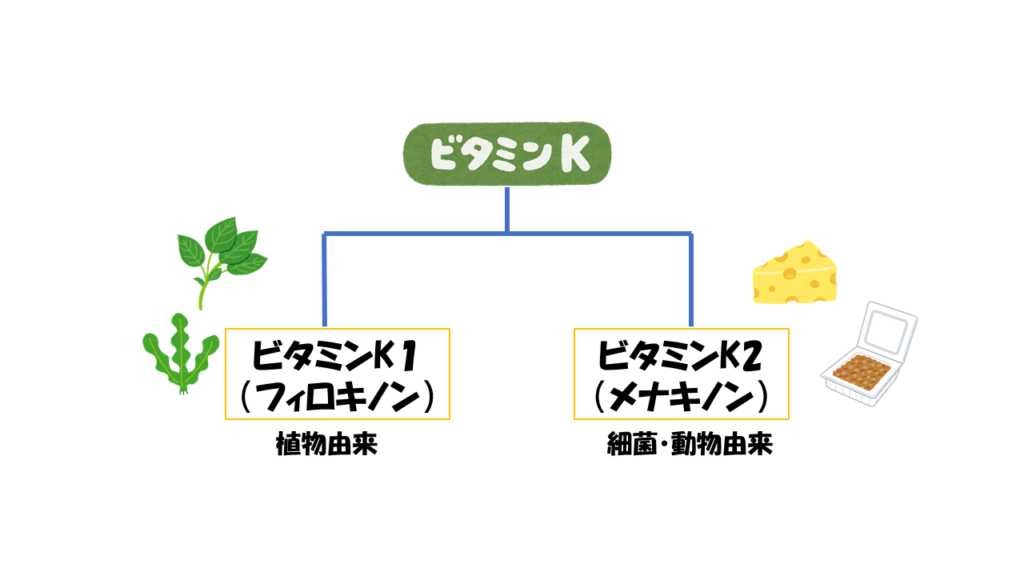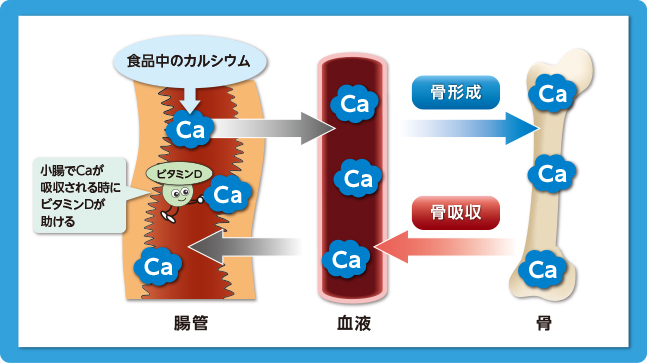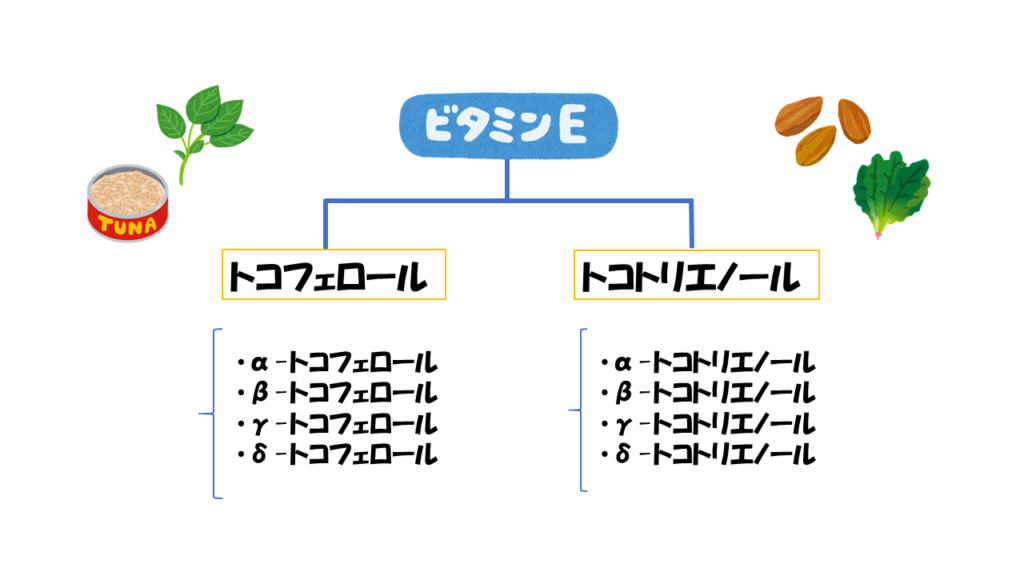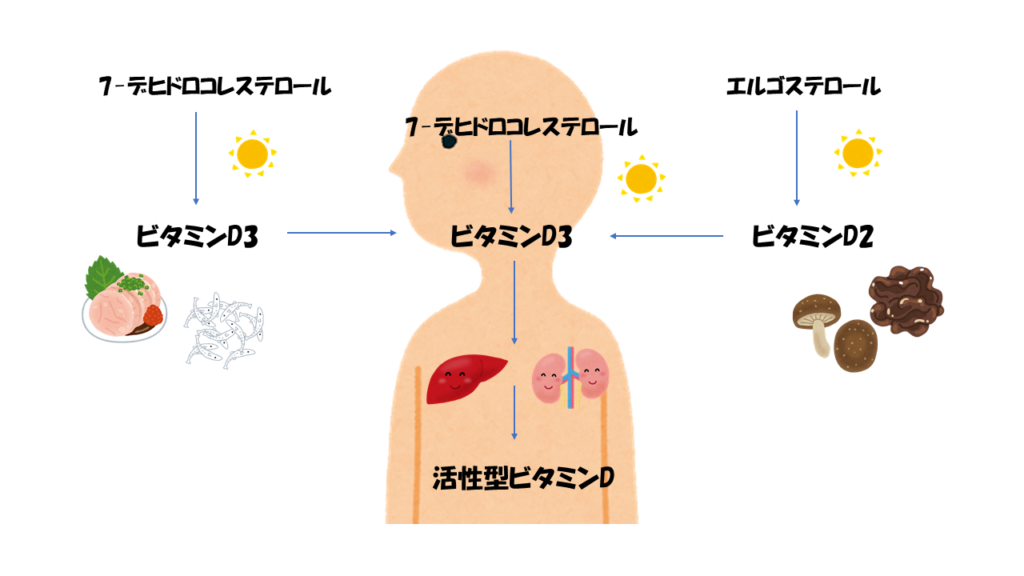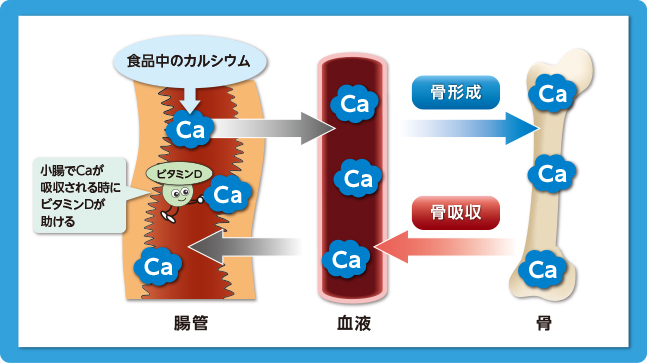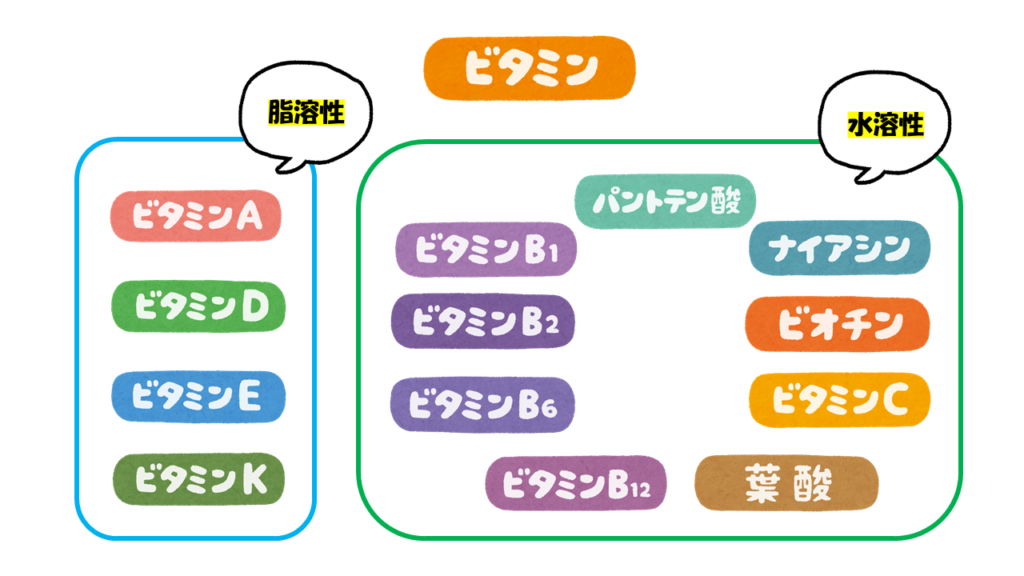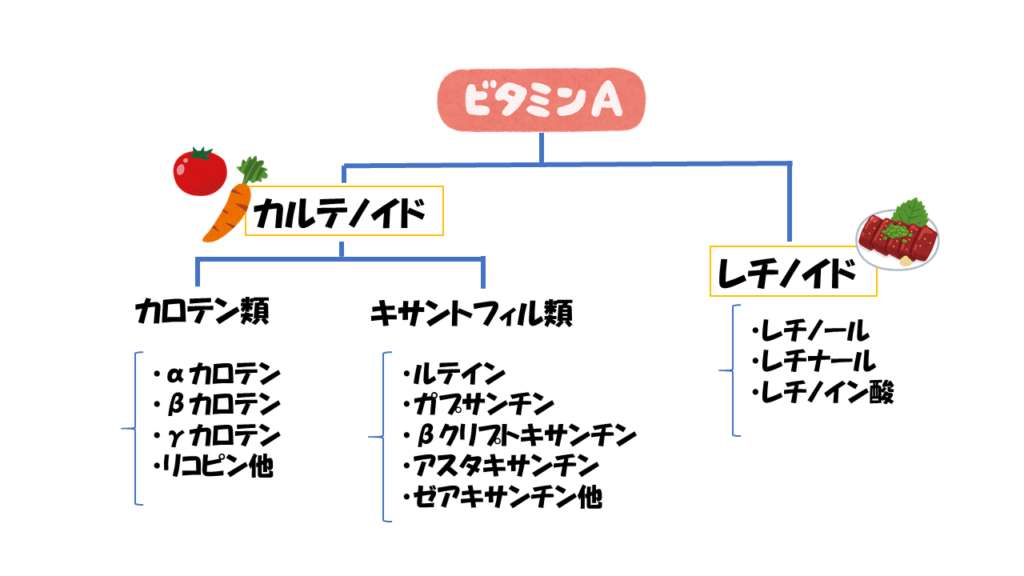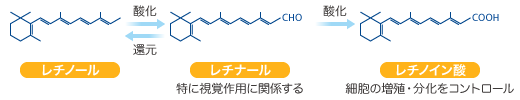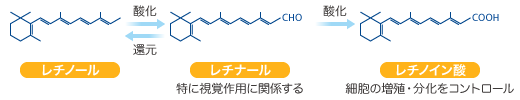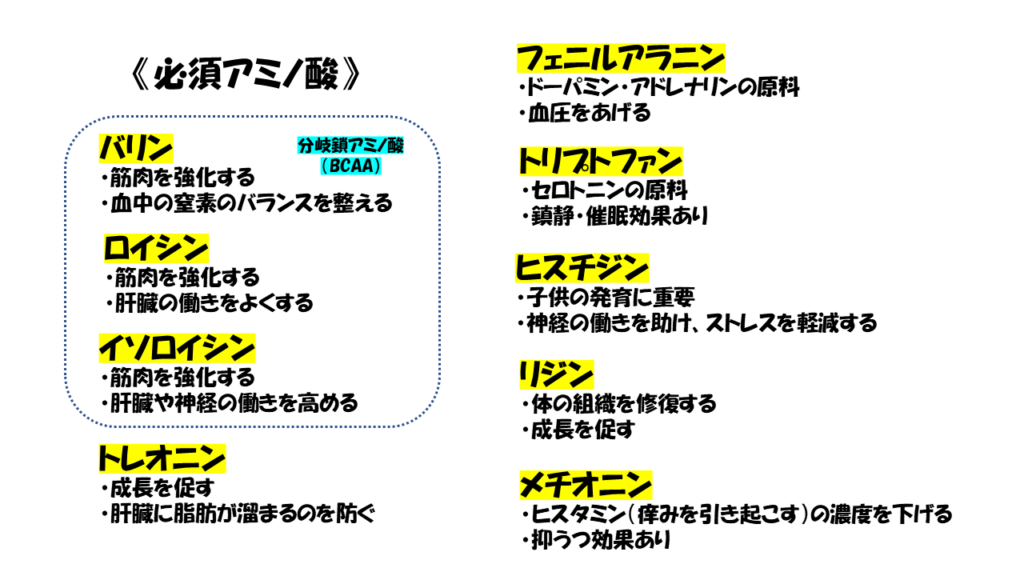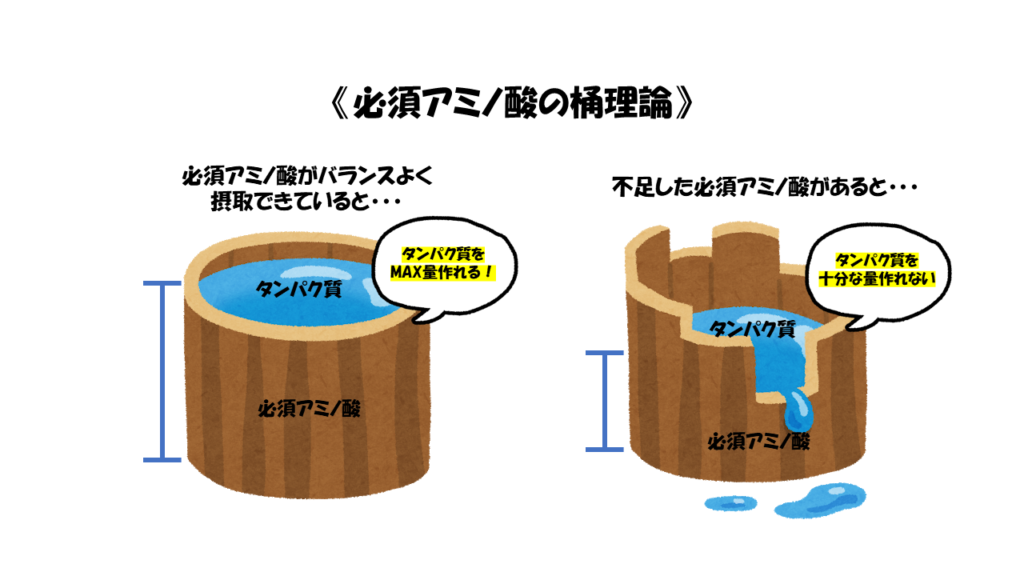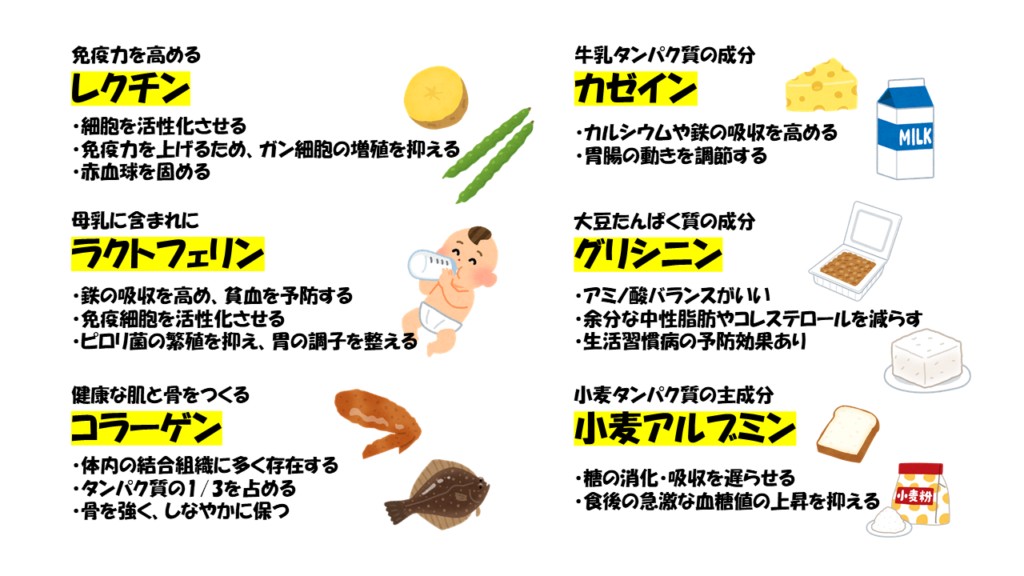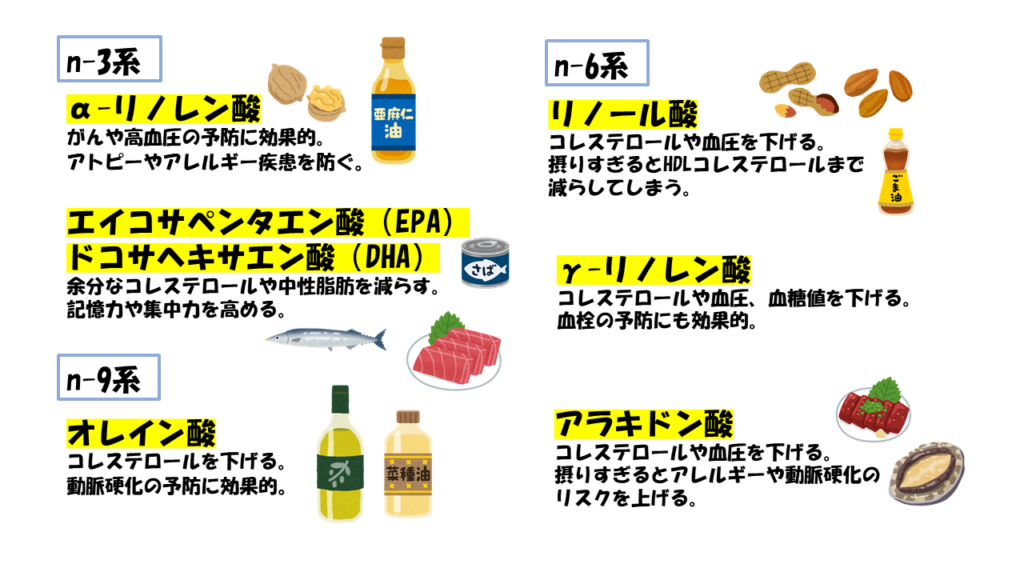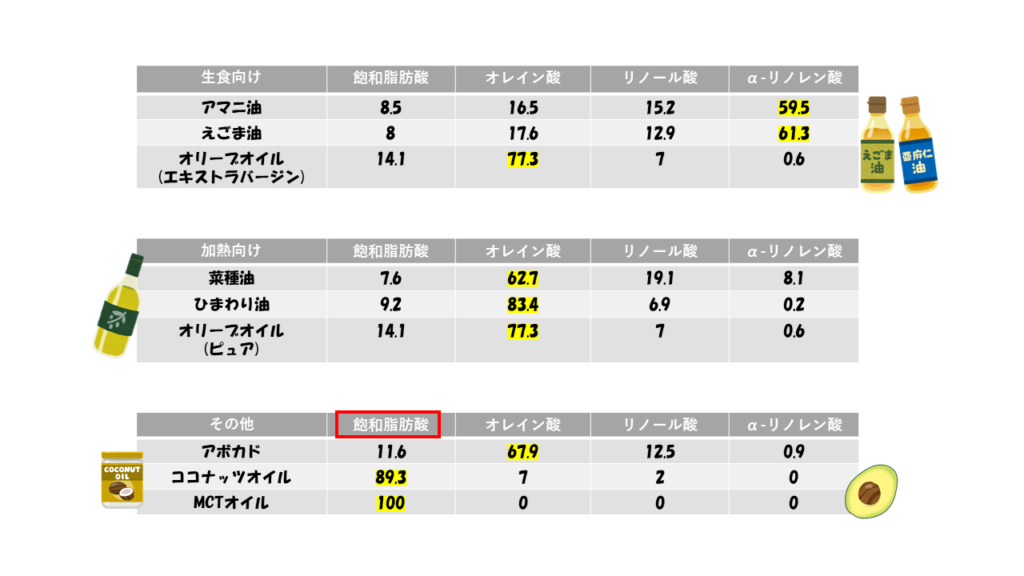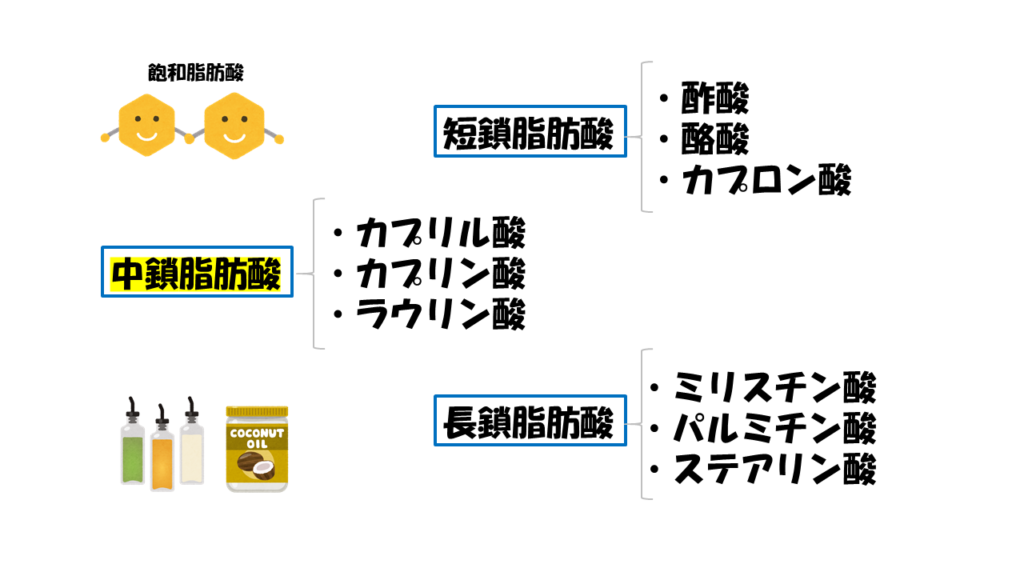今回はタンパク質についての投稿となります。
ダイエットブームの中、タンパク質を摂れ!という言葉をよく耳にしませんか?
これには理由があるんです。
タンパク質の重要性について知ってもらい、普段の食事に活かしてもらえればと思います(^^)
まず、タンパク質とは?
人間の体は十数万種類のタンパク質で構成されています。
筋肉や内臓・骨・皮膚・髪・血液・ホルモン・酵素・免疫物質などの材料として
タンパク質は利用されているのです。
では、タンパク質が不足するとどうなるのでしょうか。
①筋肉量が落ちる
過度な食事制限や運動量が多く、エネルギーが足りない場合、
筋肉を分解してエネルギーを捻出します。
人間の体の中では、タンパク質の合成と分解が常に行われていますが
この場合、材料が足りず合成よりも分解が上回ってしまうのです。
筋肉が落ちると、代謝が落ち、ダイエットの効果も薄れてしまいます。
②むくみ
血中に存在するアルブミン。
血管内と細胞の水分量を調節する働きがあり、タンパク質で出来ています。
材料のタンパク質が不足し、アルブミンが不足する(血管内のアルブミン濃度が薄くなる)と
血管内と細胞の濃度を一定に保とうとして、血管外(細胞)に水分を移動させます。
これにより、むくみの症状が出てしまいます。
③髪や肌に影響が出る
髪・肌も色んなタンパク質からできています。
そのタンパク質が不足すると、
髪が傷みやすくなる・艶が無くなる・肌のハリがなくなる・乾燥しやすくなる・・・etc
容易に想像できると思います。
女性は特に気になるところですね。
外部からのケアはもちろんですが、食事の影響を大きく受けるので
内部ケアを甘く見てはいけません。
④免疫力の低下
ウイルスや細菌が体内に入った時、体の中で働く免疫機能。
この時に働く免疫細胞や抗体の主成分はタンパク質です。
タンパク質不足により、免疫機能が正常に働いていないと
風邪を引きやすくなったり、悪化したりするかもしれません。
⑤集中力・思考力の低下
やる気や集中力に関わる神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン・アドレナリン)も、タンパク質を原料にしています。
このバランスが崩れたり、不足すると
集中力・思考力の低下に陥ってしまいます。
もちろん、タンパク質不足だけが原因でないこともありますが
こういった症状を引き起こさないためには、
必要量のタンパク質摂取が重要なんです。
続いてここからは、食事から摂取できるタンパク質について見ていきます。
代表的な6種類。
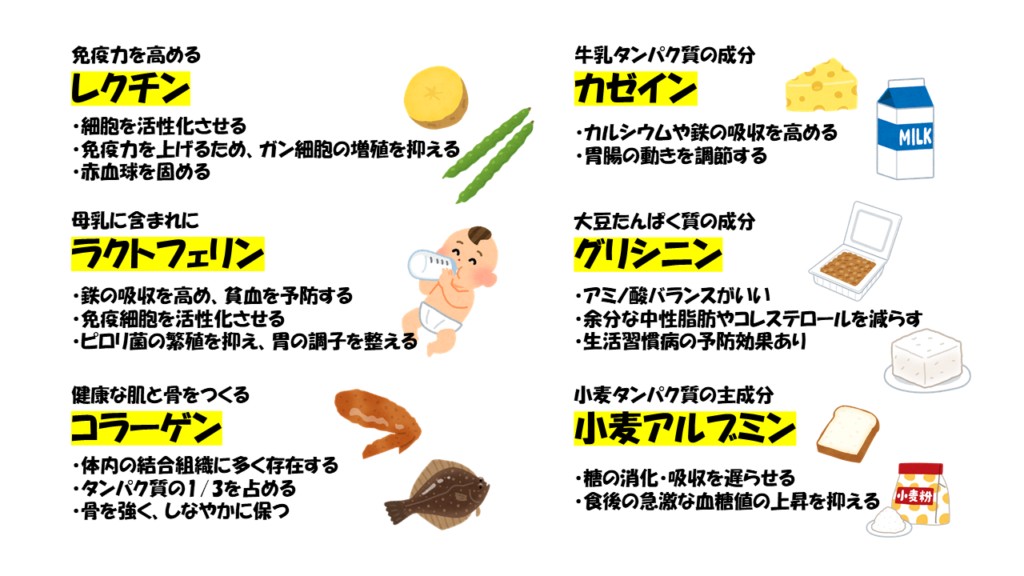 食品に含まれる6つのタンパク質
食品に含まれる6つのタンパク質
①レクチン
免疫力を高める作用があります。
豆類やナス科(ジャガイモ・茄子・トマト)の植物に多く含まれているタンパク質です。
灰汁の原因はこれです。
(茄子やジャガイモを切った後水にさらすのは、このレクチンを取り除くため。)
豆類は煮たり、発酵させることが必須!
生で食べるとお腹を壊すことがあるので、注意してください。
②ラクトフェリン
母乳に含まれる成分です。
腸に届くと作用を発揮しますが、
タンパク質分解酵素や胃酸にとても弱いため、
食事から摂取するのは難しいです。
赤ちゃんの場合、酵素や胃酸の働きが弱いため、
母乳のラクトフェリンがしっかり働いてくれます。
③コラーゲン
美肌には欠かせない成分ですね。
お鍋やスープに入れるのが流行っているみたいですが、
コラーゲンは熱に弱いので、ドリンクやサプリメントでの摂取が効率的です。
また、体内で分解されてしまうので
再びコラーゲンとして活用できる確率はあまり高くありません。
ただし、必須アミノ酸を多く含んでいるので、優秀な栄養源と言えますね。
④カゼイン
牛乳に含まれるタンパク質の80%がこのタンパク質です。
(残りの20%はホエイたんぱく)
プロテインでもカゼインやホエイ・ソイなど、いろんな種類がありますよね。
筋肉の分解を抑制する作用があり、
消化吸収が遅いため、筋トレをされている方は夜に摂取するのがオススメ。
血中のアミノ酸濃度を長くキープできるので、寝ている間も効果が持続します。
⑤グリシニン
大豆に含まれるタンパク質の約半分を占めます。
動脈硬化や心筋梗塞の予防効果も期待でき、
生活習慣病が問題視されている現代人には、積極的に摂りたい成分ですね。
⑥小麦アルブミン
小麦たんぱくの主成分です。
食後血糖の上昇を抑える作用があり、糖尿病の特定保健用食品として認可されています。
ただし、小麦製品には糖も多く含まれており、
食べ過ぎは血糖値上昇の原因となりますので、注意が必要です。
タンパク質と一言で言っても、
食品によって種類が全然違うんですね。
次回はもう少し掘り下げて、タンパク質を構成するアミノ酸について
考えてみようと思います。
このアミノ酸の種類や組み合わせが重要だったりします。
では、今日はここまでです(^^)/